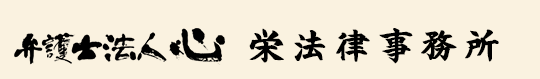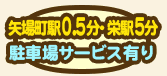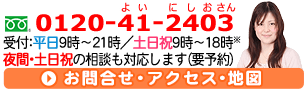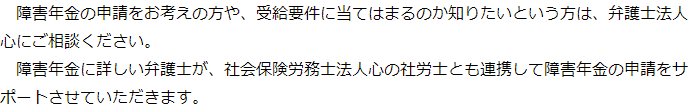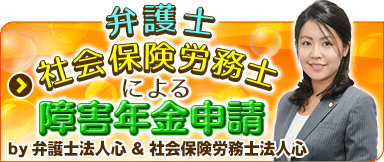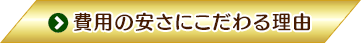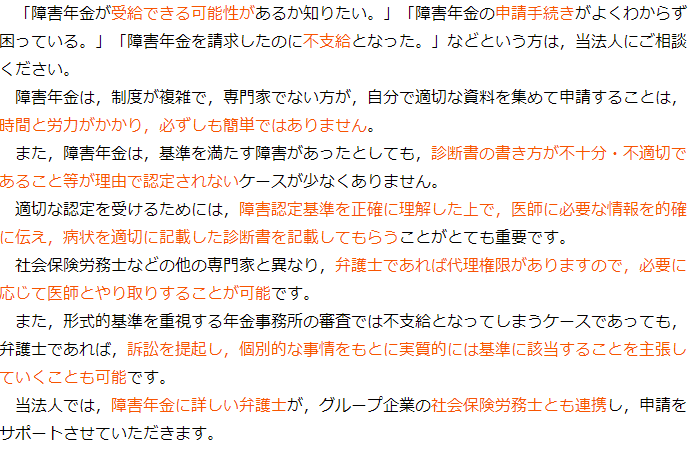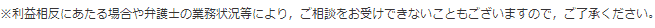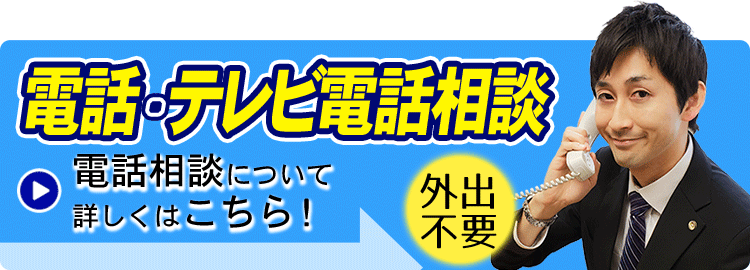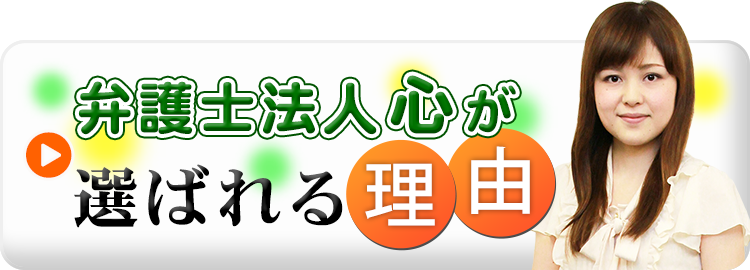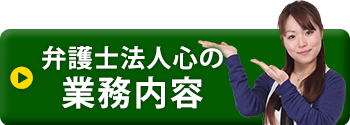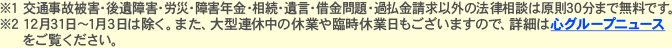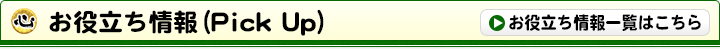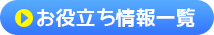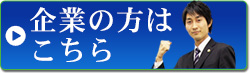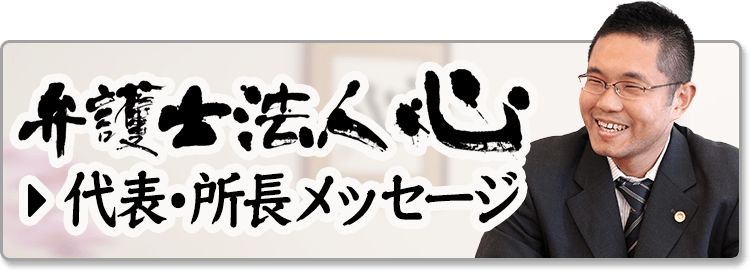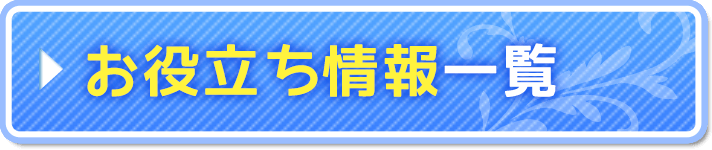障害年金
アクセスのよい事務所です
障害年金についての依頼をお考えの方も気軽にお越しいただけるかと思います。各事務所の所在地等の詳細はこちらからご覧いただけます。
障害年金申請時に必要となる書類
1 障害年金申請時に必須となる書類

障害年金申請時に、絶対に必要なる書類は「年金請求書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「金融機関の通帳コピー等」になります。
「年金請求書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」は所定の書式があるので、市区町村役場や年金事務所、日本年金機構のホームページ等で取得することができます。
また、「年金請求書」「病歴・就労状況等申立書」は、本人や代理人等で作成しますが、「診断書」は医師に作成してもらう必要があります。
なお、住民票も添付が必要な資料になりますが、請求書にマイナンバーを記載すれば提出を省略することができます。
2 初診日を証明する資料
初診日に診断を受けた医療機関・診療科と診断書を記載した医療機関・診療科が同一の場合には不要になりますが、そうでない場合には、初診日を証明する資料を提出する必要があります。
初診日を証明する資料としては、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を書いてもらうことが考えられますが、それ以外にも「受診状況等証明書が添付できない申立書」と初診日を客観的に証明する参考資料によって、初診日を証明することもあります。
また、初診日が特定しづらい病気やケガで請求する場合には、「障害年金の初診日に関する調査票」を提出することもあります。
3 加給年金や加算対象となる家族がいる場合
加給年金や加算対象となる家族がいる場合には、家族関係を確認するために戸籍謄本を提出したり、生計維持要件を確認するために課税証明書等を提出したりすることが必要になります。
4 その他の資料
20歳前傷病の場合には、所得制限があるため本人の所得証明書を添付します。
障害者手帳を取得している場合には、障害者手帳のコピーを、年金を受給している場合には年金証書のコピーを添付します。
また、遡及請求する場合には、障害認定日からの支給が認められない場合でも、事後重症請求に切り替えることができるよう、「請求事由確認書」を提出します。
障害の原因が第三者の行為によるものであるときは、第三者からの損害賠償等と障害年金を一定のルールに従って調整することが必要なため、「第三者行為事故状況届」を提出する必要があります。
障害年金は家族がいると加算されるのか
1 障害年金の子の加算、配偶者の加給年金

障害年金は、障害年金受給者に生計を維持されている子や配偶者がいる場合には、加算されることがあります。
ただ、年金の種類によって加算される場合は異なっており、障害基礎年金は、障害年金受給者に生計を維持されている子がいる場合に加算され、障害厚生年金は、障害年金受給者に生計を維持されている配偶者がいる場合に加算されます。
2 子の加算額
障害基礎年金の子の加算額は、2人目までについては、1人につき年22万4,700円×改定率、3人目以降は1人につき年7万4,900円×改定率になります。
また、ここでの子とは、障害年金受給者に生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の状態にあたる子がこれに該当します。
3 配偶者の加算額
障害厚生年金の配偶者の加算額は、等級が1級から2級の場合は22万4,700円×改定率、3級以下の場合はなしになります。
なお、配偶者が65歳以上になる、もしくは公的年金を受給する場合には、この加算はなくなります。
障害年金申請の手続きの流れ
1 障害年金申請の方法

障害年金は、年金請求書に、必要な添付書類を付けて、お近くの年金事務所や街角年金相談センターに提出することによって申請します。
申請後、日本年金機構で、障害の状態が障害年金に該当する程度かどうかや、その他の障害年金が認められるための条件に該当するかどうかの審査が行われ、障害年金の支給が認められた場合には、「年金証書」や「年金決定通知書」が、支給が認められなかった場合には「不支給決定通知書」が送られることになります。
2 障害基礎年金か障害厚生年金か
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の二つがあります。
これは、障害の原因となった病気やけがの初診日が20歳未満か、初診日に国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたかどうかによって決まります。
障害基礎年金か障害厚生年金かで提出する年金請求書も異なりますので、まずは、初診日を特定することが必要になります。
3 納付要件の確認
初診日が特定できれば、当該初診日に国民年金か厚生年金かを確認することになります。
また、初診日が20歳以降の場合には、保険料の納付要件を充たしていることも必要になります。
そのため、年金事務所等で、初診日時点において国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたか、保険料の納付要件を充たしているかどうかを確認します。
4 診断書等の取得
初診日時点において国民年金に該当するか厚生年金に該当するかや、納付要件を充たすことが確認できれば、次は、現在通っている病院や、障害認定日(初診日から1年半が経過した日)に通っていた病院で診断書を作成してもらったり、初診日についての受診状況等証明書を作成してもらうことになります。
また、これまでの症状等についてまとめた病歴・就労状況等申立書を作成します。
5 請求書の提出
診断書や初診日の証明書等が揃ったら、配偶者の収入の資料等、その他の必要書類をそろえ、年金請求書を作成し、添付書類とともに年金事務所等に提出することになります。
6 詳しくは専門家にご相談ください
以上が、障害年金申請の大まかな流れになります。
ただ、個別の状況によっては、他に必要な資料を取得することもあります。
詳しくは、弁護士、社労士等の専門家にご相談ください。
障害年金の所得制限とその内容について
1 障害年金の所得制限

障害年金は、原則、資産や収入があっても受給することができます。
ただし、20歳前に病気やケガになった方の障害基礎年金については、所得の制限があります。
これは、20歳前に病気やけがになった方の障害基礎年金については、年金保険料の納付義務が発生する前に初診日があるため受給者本人が保険料を納付していないためです。
2 所得制限の内容
所得制限については、所得額に応じ、全額年金の支給が停止される場合と、2分の1の支給が停止される場合があります。
3 所得限度額
2022年10月現在、所得制限の対象となる所得限度額は以下のとおりとなります。
- ⑴ 2分の1支給停止
- 扶養家族なし・・・370万4000円
- 扶養親族等1人あたり・・・38万円の加算
- 老人控除対象配偶者(※1)1人あたり・・48万円の加算
- 特定扶養親族1人あたり(※2)・・・63万円の加算
- ⑵ 全額の支給停止
- 扶養家族なし・・・472万1000円
- 扶養親族等1人あたり・・・38万円の加算
- 老人控除対象配偶者1人あたり・・・48万円の加算
- 特定扶養親族1人あたり・・・63万円の加算
(※1)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上の方。
(※2)特定扶養親族とは、扶養親族の内年齢が19歳以上23歳未満の人をいう。
4 所得制限の期間
所得制限による支給停止は、前年の所得に基づき、10月から翌年の9月までの期間となります。
障害年金の種類と支給額
1 障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
初診日に国民年金に加入している、もしくは、20歳前の場合には、障害基礎年金、初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金となります。
障害基礎年金には、障害の程度に応じ、1級と2級があり、障害厚生年金には、障害の程度に応じ、1級、2級、3級、障害手当金があります。
障害厚生年金の1級、2級は、障害基礎年金に加えて支給されることになります。
2 障害基礎年金の金額
障害基礎年金の支給額は定額であり、障害年金受給者に生計を維持さている子どもがいる場合は、「子の加算」があります。
支給額については、一級の場合は「97万6,125円×改定率」、2級の場合は「78万900円×改定率」で算出します。
子の加算は、子どもの人数によって額が変わってきます。
3 障害厚生年金
障害厚生年金は、収入等を基準に計算する平均標準報酬月額と厚生年金の加入月数に一定の割合を乗じて計算することになります。
また、配偶者がいる場合は「加給年金額」が付くことになります。
加給年金額は「22万4,700円×改定率」で算出します。
4 まとめ
以上のとおり、障害年金は、初診日に厚生年金に加入していたかどうかや、収入の金額、家族構成、障害の程度によって変わってきます。
詳しくは、弁護士や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
障害年金の対象となる人とは
1 障害年金には一定の条件があります

障害年金は、何らかの障害によって収入を得ることが難しくなった方に支給される年金です。
しかし、無条件で支給されるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
ここでは、障害年金の対象になる人について、ご説明します。
2 初診日要件を満たしていること
初診日という言葉は、あまり聞いたことがないかもしれません。
初診日とは、初めて医師の診察を受けた日を指します。
ただし、あくまで障害年金の請求をすることになった傷病に関して、初めて医師の診察を受けた日を指すので、全く無関係の傷病の診察は、初診日とは認められません。
初診日要件を満たしている状態とは、①初診日に公的年金に加入している、②初診日に20歳未満、③初診日に公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の人のいずれかに該当する必要があります。
3 保険料を納めていること
年金は、加入している人が納めた保険料で、困った方を救済する制度です。
そのため、保険料を納めていない場合は、障害年金を受け取ることができません。
もっとも、保険料を満額納めている必要はありません。
具体的には、初診日のある前々月から見て、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料を納めているか、保険料を免除されていることが必要です。
また、初診日のある前々月から見て、直近1年の保険料を納めているか、保険料が免除されている場合も、障害年金の受給が可能になります。
ただし、初診日が20歳より前の場合、保険料の納付義務がないため、保険料を納めていなくても障害年金の受給対象になり得ます。
4 障害の程度が基準を満たしていること
障害といっても、様々な種類と程度があります。
たとえば目の障害の場合、両目が全く見えないケースや、片目だけが見えないケースもあります。
そこで、障害年金の受給にあたっては、障害の部位や程度の基準が定められています。
障害の程度は、医師の診断書等によって、証明することになります。
障害年金が受給できるケース
1 障害年金が受給できるポイントは3つ

障害年金の申請を検討されている方にとって、最も気になる点の1つが、「自分の疾病について、障害年金を受給することができるのか」ということだと思います。
障害年金を受給できるかどうかは、①初診日、②障害状態、③年金保険料の納付の3つのポイントで決まります。
2 ①初診日とは何か
初診日という言葉をインターネットで調べると、「初めて医師の診察を受けた日」という解説がされている場合があります。
おおまかにはそのとおりなのですが、より厳密にいうと「問題になっている傷病について、初めて医師の診察を受けた日」です。
たとえば、令和元年3月に、骨折で整形外科の医師の診察を受け、令和元年10月に精神科でうつ病と診断された場合に、うつ病で障害年金の申請をするなら、令和元年10月が初診日ということになります。
障害年金の申請をする際は、この初診日が全ての基準になると言っても過言ではありません。
3 ②障害状態
障害の程度が、一定基準を満たしている場合に、障害年金が支給されます。
どんな傷病について、どの程度の障害であれば障害年金が支給されるのかは、日本年金機構がホームページで公表している「障害認定基準」に記載があります。
また、「いつの時点の障害の程度」を問題にするのかですが、これは「障害認定日」時点を基準にします。
「障害認定日」とは、初診日から1年6か月が経過した日を指します。
4 ③年金保険料の納付
障害年金は、年金制度である以上、原則として保険料を納めている人しか受給できません。
たとえば、自営業者の方は、国民年金の保険料を払う義務がありますが、保険料を全く払わないままにしていた場合、障害年金の受給は難しいということになります。
もっとも、年金の保険料を納付していない時期があっても、必ず障害年金が受給できないわけではありません。
たとえば、年金の加入期間の3分の2以上は保険料を納めていたか、保険料が免除されていれば、年金の納付要件は満たしたことになります。
また、初診日から直近1年間は保険料を納めていた場合も、障害年金を受給できます。
さらに、20歳より前に初診日がある場合、保険料を納める義務がないので、保険料の納付はそもそも不要ということになります。
障害年金のことは弁護士にご相談ください
1 適切な障害年金受給に向けてサポートします

障害に対して適切な金額の障害年金を受給するためには、必要な書類を適切に揃え、審査機関に対して障害の程度をきちんと伝える必要があります。
こういった対応に関して、大変だと感じる方や、不安がある方もいらっしゃるかと思います。
障害年金に詳しい弁護士にご依頼いただくと、弁護士が申請を代行できますし、様々な点でアドバイスをさせていただくことも可能です。
手続きのやり方が全く分からないという方、うまくできるか不安がある方などは、弁護士にご依頼ください。
2 お気軽に当法人までご連絡ください
当法人には、障害年金に関するご依頼を集中的に担当する弁護士が所属していますので、障害年金の申請について安心してお任せいただけます。
栄の事務所は松坂屋の店内にありますので、ご相談にお越しいただく場合に非常に便利です。
当法人に障害年金のことをご相談いただく場合、相談料は原則としていただいておりませんので、ご相談をお考えになっている方は、まずはお気軽にご連絡ください。
当法人への障害年金のご相談に関するお問合せは、お電話やメール等にて承っております。